「鍼灸に興味はあるけれど、実際どれくらい効果があるのか分からない」「何回通えばいいの?」「効果が感じられないけど大丈夫?」—— そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は
- 鍼灸の効果がいつから現れるのか
- 鍼灸の効果と持続性
- 「効果を感じない」ケースの理由
- 腎臓などの内臓に対する影響
について鍼灸師の視点から解説していきます。
鍼灸とは? 〜自然治癒力を高める東洋医学〜

鍼灸(しんきゅう)は、東洋医学の代表的な治療法の一つで、体にある「経絡(けいらく)」と呼ばれる 経穴(ツボ)に沿って、鍼やお灸を施すことで、自然治癒力を高め、さまざまな不調を改善していく方法です。
1979年に世界保健機関(WHO)にて48疾患が鍼灸の適応であると定められています。
定らえている疾患は以下のようになります。
神経系疾患
・神経痛 ・神経麻痺 ・痙攣 ・脳卒中後後遺症 ・頭痛 ・めまい
・自律神経失調症 ・不眠 ・神経症 ・ノイローゼ ・ヒステリー
運動器系疾患
・関節炎 ・リウマチ ・頚肩腕症候群 ・頸椎捻挫後遺症 ・五十肩
・腱鞘炎 ・腰痛 ・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)
循環器系疾患
・心臓神経症 ・動脈硬化症 ・高血圧低血圧症 ・動機 息切れ
呼吸器疾患
・気管支炎 ・喘息 ・風邪および予防
消化器系疾患
・胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘) ・胆嚢炎
・肝機能障害 ・肝炎 ・胃十二指腸潰瘍 ・痔疾
代謝内分泌系疾患
・バセドウ氏病 ・糖尿病 ・痛風 ・脚気 ・貧血
生殖、泌尿器系疾患
・膀胱炎 ・尿道炎 ・性機能障害 ・尿閉 ・腎炎 ・前立腺肥大 ・陰萎
婦人科系疾患
・更年期疾患 ・乳腺炎 ・白帯下 ・生理痛 ・月経不順
・冷え性 ・血の道 ・不妊
耳鼻咽喉科系疾患
・中耳炎 ・耳鳴 ・難聴 ・メニエル氏病 ・鼻出血 ・鼻炎
・ちくのう ・咽喉頭炎 ・へんとう炎
眼科系疾患
・眼精疲労 ・仮性近視 ・粘膜炎 ・疲れ目 ・かすみ目 ・ものもらい
小児科系疾患
小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)
・小児喘息 ・アレルギー性湿疹 ・耳下腺炎 ・夜尿症 ・虚弱体質の改善
鍼灸の効果はいつから感じるの?

「鍼灸ってすぐに効くの?」という質問をよく受けますが、結論から言うと、個人差が大きいです。
初回から効果を感じる人もいれば、数回かかる人も
- 即効性があるタイプ:筋肉の緊張が原因の肩こりや頭痛などは、1回の施術で「体が軽くなった」と感じることがあります。
- 継続が必要なタイプ:自律神経失調症や腎機能の改善などは、3〜5回以上で徐々に効果を実感できることが多いです。
効果を感じるまでの期間の目安
| 症状の種類 | 効果を感じ始めるまでの期間 |
|---|---|
| 筋肉疲労、肩こり | 1〜2回目で実感する人も |
| 自律神経の乱れ | 3〜5回目あたりから |
| 内臓機能(腎臓など) | 1ヶ月以上かけて改善傾向 |
鍼灸の効果が「感じない」ときの理由

鍼灸を体験したことがある人に話しを聞くと「効果が凄くある」という意見と「効果を全く感じない」という意見の極端な意見を聞くことがあります。
鍼灸は生体反応を利用し効果を得る施術になるので、体調や生活習慣、個人の感覚によって効果の感じ方が変わります。
この項目ではどういった状況で効果の感受性がかわるのかご紹介します。
体質の違い
鍼灸の刺激が入ると刺激を入れた周囲の血管が拡張することで、効果を得ることがえできます。
なので、冷えや血行不良が強い場合は、効果が出るまでに時間がかかることがあります。
生活習慣の違い
鍼灸は自律神経にも働きかけることで、症状の改善を行います。
食事や睡眠、ストレスにより自律神経のバランスが乱れていることで、効果を感じにくくなる可能性があります。
感受性の違い
鍼灸の刺激を同じようにしても個人で受け取り方が変わります。
刺激量が少なければ効果を感じにくく、刺激量が多くなることで気怠さを感じることがあります。
鍼灸の効果はどのくらい持続する?
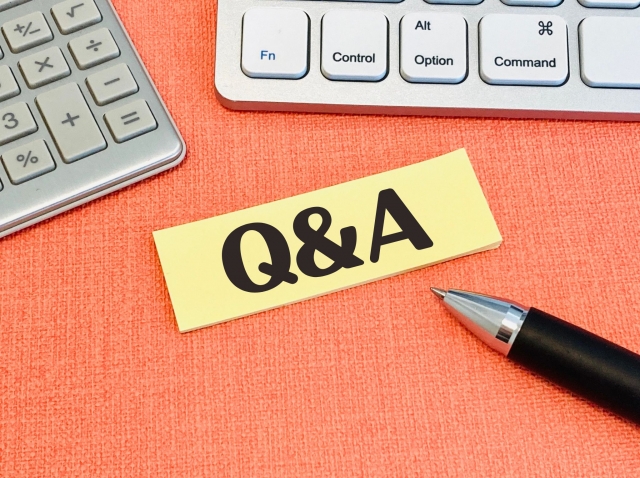
最初は一般的に数日〜1週間程度の持続が多いです。
鍼灸を続けることで、血液を循環させやすくしたり、自律神経の働きを活性化させることで
体質を変え症状を根本から整えていく施術方法になります。
根本から体質を整える場合、週に1回~2回の施術を2、3か月継続することで
症状が軽快していく例が多くあります。
鍼灸は腎臓などの内臓にも効果がある?

鍼灸は、筋肉や神経だけでなく内臓機能の調整にも有効です。
直接内臓に影響を与えるのではなく、内臓に流れ込む血流量を増やすことで、内臓の調整に役立ちます。
また、鍼灸は自律神経にも働きかけます。
自律神経は内臓の働きと密接に関係しているため、自律神経のバランスが取れることで、内臓の調整に役立ちます。
特に「腎(じん)」は東洋医学で重要視されており、腎機能は生命力や老化、免疫力にも関わると考えられています。
腎の不調に対応する症状例
- 腰痛
- むくみ
- 頻尿・夜間尿
- 冷えや疲れやすさ
- 育毛、脱毛など髪の毛に関するもの
まとめ:鍼灸は「じわじわ効く」からこそ継続がカギ

- 鍼灸の効果は世界保健機関(WHO)にも認められている
- 効果の感じかたには生活習慣や体質により個人差がある
- 鍼灸は内臓にも効果を発揮する
鍼灸は魔法のように一瞬で体を治すものではありません。効果を実感するには、一定の「期間」と「継続」が必要です。
「効果を感じない」と思っていても、体の内部では変化が起きているかもしれません。焦らず、自分の体と向き合いながら、 信頼できる鍼灸師とともに続けてみてください。
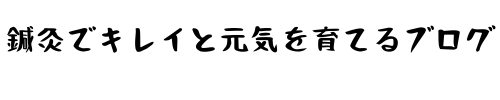
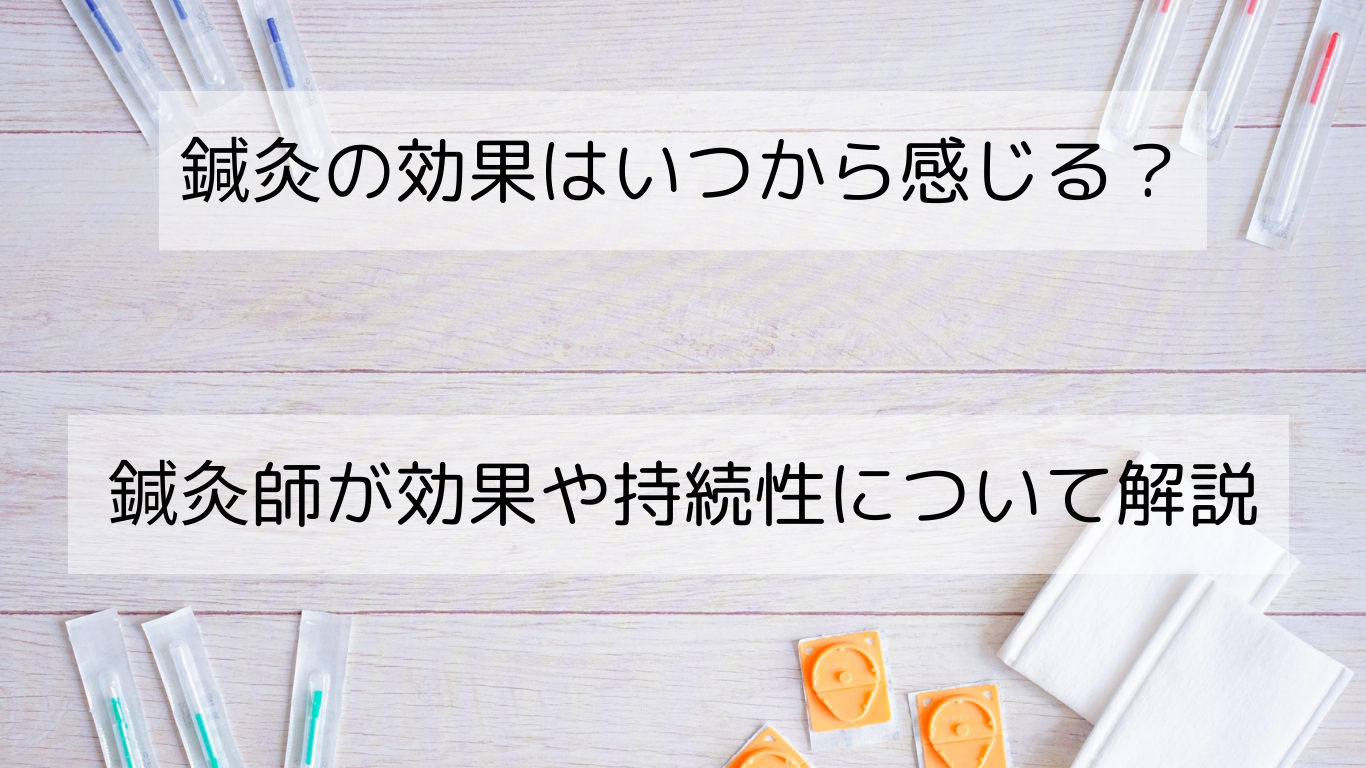

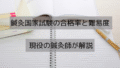
コメント